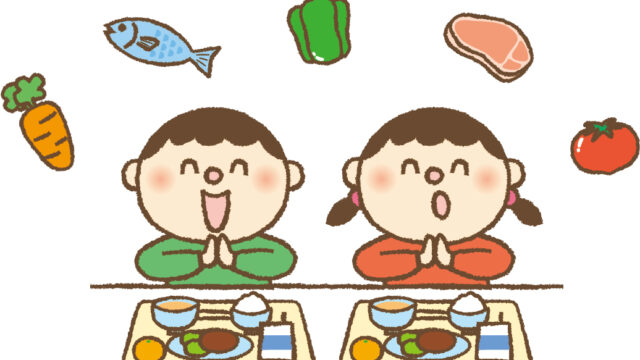なぜ 保育士を辞める人は多いの?
あこがれと現実の間
夢と憧れを持ち、保育士の資格を取り、ようやく採用試験に受かり、
夢と希望に満ちた保育士生活が始まります。
でも、離職率が高いのはなぜでしょうか。
数年前の 夏の全国保育合研(全国保育団体連絡会 合同研究集会)でも、
1年や数年で辞めてしまう人の多さが語られていました。
実習生担当の大学教授が、ベテラン先生たちに向けて話していました。
「夢と希望に溢れ、目を輝かせて卒業した生徒たちが、
表情を曇らせて、悩み落ち込み 自信をなくして相談に来る。
相談に来る生徒はまだいいが、顔も出さないまま、
もう1年後には 辞めてしまっていた という生徒さんも多い」 と
悲しそうに話していました。
「先輩が 良かれと思ってするアドバイスも、
『自分にはそんな事できない』という 自信のなさにつながる若い子も多い」
ということなどを話し、
「新採職員や価値観の違う職員のことも
園の子どもたちと同じように あたたかい目で見て、
いいところを認めて褒めて伸ばして
大切に育てていって欲しい」と訴えていました。
きっと、この大学の先生のところには、先輩保育者から言われた言葉に
傷ついてくる人が多いのだろうな と思える訴えでした。
離職原因いくつかあげてみます
人間関係の他にも、きっと
今は、様々な仮説はあるものの 昔に比べて発達障害の子どもが増え
子育ての環境も大きく変わり、愛着障害などの問題も増え
これまで多くの園で行われてきた 一斉保育での対応では
難しいお子さんが 増えていると言われています。
保護者も、一昔前に「モンペ」(モンスターペアレント)
ということばが流行りましたが、
保護者のクレームもバラエティにとんで、質も様々になっています。
核家族化も当たり前になり、相談する人が身近にいないために、
保護者にも、これまでの子育ての常識が通用しにくくなったと感じている
ジェネレーションギャップ(世代の違いにより、価値観の違いを感じる)もあるようです。
情報は豊かになりましたが、それも返って混乱を招く場合もあり、
個人主義で、お互い様の精神が薄くなり、
トラブルや怪我に対しても おおらかになれない方は増えている印象があり、
保護者対応の難しさを感じます。
ご近所トラブルも昔より増えており、
「子どもの声がうるさい」という苦情が入る園も 実際にあるのです。
そして、どこの職場にもある人間関係問題
職員同士のコミュニケーションは、
保育観の違いから 派閥が生まれ
難しくなるケースが大半です。
さらに、毎日の子どもとの 生活や遊びの時間(保育)を
ただ楽しんでいればいいわけではなく、
(もちろん楽しく過ごすことは大前提です)
子どもたちの成長や目標達成のために、
計画案を立て、実施事項や反省点を記録します。
事務上の問題だけではなく、話し合いは重要で、
自分の考えと、複数担任なら担任内の共通理解を図り
その考えが子どもにとって最善の利益をもたらすものなのか、
園目標に合っているのか、など管理職を含め
他のクラスの職員にも、確認してもらう必要があります。
目標が決まって、具体的な内容、
例えば 制作や運動など、何かをするためには
一つひとつ、準備は必要なのです。
毎日のやるべきことの多さが、実は尋常じゃないのです。
そのうえ、一般的なお給料に比べると・・・
今はそれでも 一昔前よりは 少しは良くなっている印象はあります。
「なぜ、こんなに大変な仕事なのに」と言う声を出せば、
「お金のことを言うなんて、保育者としての資質がない」
などと言われたりします。
お金のことより子どものことを第一に考えて
文句を言わずに 一生懸命働くことが美徳とされる
保育者の心は とてもきれいなもの とされる風潮は今でも残っているようです。
ちょっとまって。そんなんじゃ 保育士になりたくないよ
ですよね。
それでも、ご褒美があるから頑張れるのです!
そのご褒美とは・・・?
保育士をやっていてよかった
そう思えるのはどんなときでしょう。
それは、
子どもたちの笑顔と
保護者からの感謝の言葉
上司からのねぎらいの言葉
後輩から頼りにされ、ベテランの力を借り、
同僚とより良い保育についてチームでアセスメントする
そんな充実感 だったりするのです。
あと、おいしい給食と、自然の中の散歩も最高!
現場を離れてみてわかったけれど、
本当に体と心に健康的な 贅沢な毎日を過ごしていたと思います。
そして、なんと言っても
日々の感動!
これにつきます。
毎日起こる出来事の中に、子どもたちとのストーリーが必ずあり
泣き笑い怒り悲しみ いろいろな出来事を通して
子どもとともに考え 職員や保護者とともに悩み
やり取りを通して 相手から学び 自分を知り
解決策が見つかったり、いつの間にか解決できている時
達成できた時
そんなときの喜びはひとしおです。
最終的には ドラマ顔負けの感動が待っています。
そういうことばかりではない こともあるけれど
今起きている 不快に思える出来事も、
いつかは、『その出来事があったおかげで 今がある』
と感謝できる体験を 何度も重ねて来ることができました。
卒園式で成長を感じる
毎日の生活を一緒に過ごすことは、当たり前のことではない
ずっと続くわけではないのです。
人生の中の 就学までの数年間
かけがえのない 大切な乳幼児期に
携わらせていただくことができることを ありがたいと思います。
年長児になれば皆 卒園する。
赤ちゃんの頃から一緒に過ごしてきた子どもに関しては、
一緒に泣き笑いした 思い出がありすぎて、
成長した姿をみると 卒園式(進級式)は感慨深いものがあります。
卒園式は毎年あるけれど、
一人ひとりが違うから
毎年違う感動があるのです。
私はそんな区切りの場面があることで、日々の保育のすばらしさをとても実感し、
子どもたちの成長のストーリーに感動し、
自分も成長させていただいていることに気づき、
子どもたちや保護者や職員や地域の方や
いろいろな方に感謝をしています。
こんな感動が味わえる職場は なかなかないと思います!
むしろ、大きな出来事でなくても、
日々の小さな中に、可愛らしいエピソードも満載だったりします。
そんなかわいいエピソードも いつか
お伝えしていきたいな と思っています。
辞める理由
私の周りの定年退職と結婚退職した方以外の理由(本心や本当の理由は知りませんが)発表
・体を壊した(腰を痛めたなど)
・家族の介護を優先したい
・自分の子どもに向き合いたい
・職場の人間関係に心が疲れた(保育観の違い、承認されない)
・給料が安い(業務量の多さや重責任の割には、世間的に認められていない安さ)
・多忙さ(自分の時間がとれない)
・自分には向いていない(自信をなくした、良い保育ができない)
など
保育職を選んだ理由
ひとはそれぞれ 色々な思いを持って就職すると思います。
特に、資格を取る保育士は、それなりのポリシーを持って
保育の仕事に就く人が多いと 個人的には思っています。
子どもが好きだ とか、
未来を作り支える子どもたちを育てたい とか、
働く保護者が安心して働けるように、あたたかい家庭のような保育をしたい とか。
なかには、「資格の中では取りやすかったから」 とか
動機が不純な方もいますが。
(それで資格の取れる学校に通わず、国家資格を自分でサクサク取れちゃうのはすごい!)
生活のために保育士をしている という方もいましたが、
保育士の資格を取ろうと思った時点で
それなりの理由はあったと思いますし、
採用面接ではきっとどの方も、素晴らしい理念などを語られていたことでしょう。
それが本心だった方には思い出していただきたい。
本心を語らずに、受かるための文章を暗記したという方にも、
そう言葉にして採用されたときの 初心や誓った言葉を 忘れないで働くことができたら
素晴らしい保育が展開されるのだと思います。
でも、人は初心や理想を忘れてしまう生き物です。
毎日、目の前の忙しさに追われて
ついつい自分の理想とかけ離れて、理想と現実のギャップに葛藤しながら、
いつしか葛藤さえ することもなくなっていく。
そして、初心や理想を忘れずに
葛藤が続く人は、喪失感が生じ 心の状態が悪くなり、
気持ちや思考のコントロールができなくなり
疲れて辞める選択をしてしまう。
自分が思う「良い保育」をしたくても できない自分への不甲斐なさ
わかりあいたい(自分が正しい)思いが強すぎて
変わらない現実(相手)を受け入れられない 自分の頑なさ
柔軟な考え方や 人への思いやりを持つことの心の余裕がなくなり
人も自分も許すことができなくなる
そして辞める
という決断をする。
私の周りの 優秀で 真面目で
優しくて 思いやりがあり
子どもにも保護者にも人気があり
明るく笑顔で元気いっぱいだったあの人も、
穏やかなこの人も、
意欲的なあの人も、
お休みしたり、
お休みのあとそのまま辞めていかれたり、
お休みもせずに、辞めていかれてしまいました。
私に何ができるのか? 考えた過程と結果
私の願い
もうこれ以上優秀な人材に、
自信をなくしたり
自分を傷つけて
辞めていくことをやめてほしい。
そして考えたのです。
「そのために、先生の卵の先生になろう」と。
私は保育の道を選ぶ人たちに向けて
こんな人になってほしいな
という願いを込めて
保育に関する知識や技術内容の伝達だけではなく
いろいろな人がいるからいいんだよ
ということを子ども理解だけではなく
職員自らがわかりあえるようにしたい。
自分理解 つまり自分の強みを生かして
他者理解 他者の強みも生かして
みんなで一人ひとりの違いを 認めあい 支え合い
一人ひとりを大切にして
必要だと価値を認め
あたたかいマインドを育てていきたい
そう思うようになりました。
保育観の違いによる人間関係の悩みが
自分の周りでは多かったため、
そこをどう変えるか、どう折り合いをつけるか
環境を変える 人を変える 自分を変える・・・?
いろいろな選択肢がある中で、
本当にそれがいいことなのか?できることなのか?
選択肢は「辞める」一択ではないことを知った上で、
同じ選択結果をするとしても、
良いエネルギーを持って次に向かっていけるように
せめて、保育の仕事に二度と向き合いたくもないと
大嫌いになったまま辞めていくことだけは
避けてほしいと考えています。
人様の気持ちだから、自分がどうこうできるものではないことも
わかってはいるのですが。
大好きな保育の仕事をしてきた 自分自身を褒めて認めてほしい。
保育の仕事じたいを大嫌いになって辞めていかれるような
そんな人や環境をつくりたくない。
そのために、何ができるか
自問自答しつつ まだ模索中です。
そこで、一案として 現実に近づくために
「保育士や幼稚園教諭を目指す学生たちに
専門学校や大学で、講師として自分の経験や学んだことを
伝えていける仕事をしたい」
「そのためにはもっと子ども理解を深めたい」
そう思い、まず私は 職場の異動ができないか 希望を出し
そして、大学で学び直そう!と思いました。
まずは 教育学部で再学習し、学士の学位を取得する目標を立てました。
その後、大学院に進んで、さらに学びを深めたい と考えています。
そして、本当にありがたいことに
発達支援という 新たな職場で学ばせていただけるお話を
いただくことになりました。
保育も発達支援も奥が深すぎる
しかし、今となっては、発達支援の奥の深さを
甘く考えていた自分が恥ずかしい(*_*;
知れば知るほど
怖いもの知らずで 突っ走ってきた感がありますが
今更ながら 怖くもあり
もっともっと学びたい気持ちに 改めてなっています。
発達支援を長年続けているから というだけではない
人柄もよく 頭も切れて 優秀な職員から
たくさんのことを学ばせてもらっています。
私自身は、療育施設にいたときの経験と
子育てで苦労した分、独自に研修に行き学んだ知識と経験と
保育園での経験と
色々あるように思われるかもしれませんが、
それだけではまだまだ足りないことだらけです。
持って生まれた 資質・能力として足りないところも理解しつつ
得意なところは活かし、
言い訳せずに 自分で努力できるところはカバーし
資源(人や環境など)を使わせていただき
足りないところをフォローしていきたいと思っています。
感謝や謙虚さを忘れずに
でも 支援を必要とする人が不安にならないように
自分自身に自信も持てるように
これからも学ばせていただきます!!
学ぶって楽しい!
研修
研修もこの頃は工夫されて、単調な講演会スタイルはだいぶ減ってきています。
もちろん、内容が興味あって面白ければ、そのスタイルでもいけます。
昔45分〜50分間座り続けて 6時間授業を毎日受けてきた実績がありますので^_^
少々の退屈には耐えられる自信はあります!!
しかし今はどの研修も「参加してよかった!」と思えるような工夫や内容になっています。
大学
大学の授業も、私の想像を遥かに超えて
楽しく面白いものになっていました!
学校の授業とは、うん十年とブランクが有りました。
学び始めてわかったこと
「教育(授業)の内容も方法も時代とともに変わる」
ということです。
そして、私が学んだ時には無かった新しい情報がたくさんあり
本当に勉強になりました。
もしかしたら、昭和の当時
自分が授業を ただ単に聞いていなかっただけのこともあるかもしれませんが。
平成・令和(くくりが雑)は、講義する先生方の教え方も
いわゆるAL 【アクティブラーニング】で
「主体的・対話的で深い学び」
を意識した授業になってきています。
学びやすくてわかりやすい!! 感動・感激でした。
(ちなみに、昭和の時代でも、AL的授業を展開していた先生もたくさんいます)
同じ授業を受けた生徒同士も グループワークや意見交換
アイスブレイクなどを通して 強い結びつきが生まれ、
授業が終わる頃には 皆笑顔になり、仲良くなれるのです。
それが 当たり外れなく、どの先生も なのがすごいところ。
(私の通わせていただいている大学の 私が受けた授業は)
一方的な話をただ聞かされる授業ではないのです。
お金を払う価値があると、実感できる大学の授業内容でした。
自分が先生になったら このような授業ができるかな?
こんなふうに勧めていくのも わかりやすくて楽しそう
など、色々とアイデアが浮かび、
大学に向かう電車の中で、メモを取ったりもしました。
コロナで対面からオンラインへ
でも、そこにコロナがあり、
リアルの授業はなくなりました。
そして、オンライン生活を余儀なくされ
私は もう一度 夢を考え直すべく
霧に包まれた森の中を さまよい歩く
迷子のようになってしまいました。
だから、私は 発信する?
ADHD気質 炸裂!
新しもの好き
楽しみにしていた 対面授業が当たり前にできなくなってしまったことに
当初はショックを受けていました。
でも、職場でオンラインでの相談や指導が導入されて扱いも難しくないことがわかり、
家でも初めてZoom研修に参加してみました。
そして、「昭和時代のアナログ人間の自分が
こんな先進的なことに参加できている!」という喜びを感じ(笑)
少しずつZoomの扱いにも慣れてきました。
わざわざ遠くまで移動しなくても良いので
大切な時間やお金の節約ができることは大きく、
今までは参加をためらっていた遠くの土地での研修に
オンラインならば気軽に参加できるようになりました。
学級経営の問題も、グループディスカッションなどで補うこともできるし
オンライン研修・オンライン授業も 悪くないなあ と思いました。
敬遠していたことに チャレンジする時が来た!
Zoomを扱えるようになり 自信をつけた私は、
YouTubeも並行してよくみるようになり、
影響力の大きい講演家の方のお話を聞くようになり、
ブログを発信してみるのもいいかもしれないな、
大学でなくても、講演家のように発信する方法もあるのか
などと思い始めました。
実現できるか無理だとか、あまり深く考えないタイプなので。
そして、
「大学のセンセイもいいけれど、
こんなふうにオンラインで
発信すればいいのだ!」ということに
今更ながら気がついたのです。
YouTubeでも Instagramでも Twitterでも ブログでも Clubhouseでも
なんでもいいじゃん。リアル(対面)でなくても。と。
昭和時代の人とのふれあいを大事にする価値観の中育ってきた世代のため、
オンライン授業や研修には
あたたかさがないのではないか
と言う思いも拭いきれませんでした。
お便りも、ワープロ(という言い方が古い^_^;)の文字ではなく、あたたかい手書きで!
と指導された時代に育っているので。
でも、あたたかさもいいけれど、
新しいことへの興味関心 ワクワクのほうが強かったのです。
先生よりも、もっと手軽に発信できる方法がこんなに身近にあったのだな、
ということに気が付いたら、なんだか目標が身近になり、
迷子になってしまいました。
0か100かの私だったことにも気がつきました。
「0から100の間もあるよね、ということ。思い出して!」
自分に自問自答していました。
私は本当に 保育の価値を高めて広めたいのか
それから、学ぶ中で更に気がつきました。
せっかく保育士になった人に
「自信をなくしたりして 辞めてほしくない!」
そんな思いから
保育の価値を高めて広めるために
発信することを決めたものの、
でも それって、押しつけではないか?と 思うようになりました。
そんな思いからの私の発信を 辞めた人たちは望んでいるのだろうかと。
それよりも、今から保育を志す人や 今悩んでいる保育士さんたちに
「自分に自信をなくさないでほしい
人には人の良さ、強みとなるところが必ずあるから。」
そのために、「保育の価値を多くの人に知ってもらえますように」
という思いからの発信ならば、今は少ししっくりきます。
「保育をする方が 誇りを持って働ける環境を作っていける一助になりますように」
その思いは今もあるのだけれど、ちょっと段階を飛び越えて
スモールステップでは考えにくい事になっていることにも気が付きました。
まずは、「人(私)から言われたから」ではなく
自分を知り、自分から本当に保育のことが好きだと言う気持ちや
意欲を持ってほしい。
そんなふうに思うようになりました。
保育をする人も 違う道を選ぶ人も 応援したい
ニシトアキコ学校で学んだこと
そして、「辞める」という選択をした仲間に対して、
マイナスなイメージを持っていたのは私の受け止めの問題であって
本当はマイナスなことではないのかもしれない と思うようになりました。
それは その人が自分で選んだことだから。
私が止められることではないし、
別の素晴らしい道が待っているかもしれない。
だから、辞める選択をしたことを
マイナスに捉える必要はなかったのだと 今は思えます。
そして、彼女たちには「いい仕事をした。いい体験をした。」
と満足して 自分に自信を持ち続けて これからを生きていって欲しい。
自分の最良の道をみつけるために 次へのステップとして
輝いていってほしいと願っています。
なので、
せっかく保育士になった人を「やめないで!」
と 引き止めるために、
なにか働きかけたい と言う思いが
ブログを始めるきっかけの一つであったことを告白しつつ、
今は考えが変わってきたことも 書かせてもらいました。
このように考えられるようになった背景には
ニシトアキコ学校で学んだことが 大きく影響しています。
「起きた出来事に いいも悪いもない。」
「人間万事塞翁が馬」
「起きた出来事が悲しいのではなく、
起きた出来事を悲しいと思う自分の心が悲しんでいるだけなのだ。」
「今は悲しく思えても、いつかこの出来事があったからこそ、
素晴らしい今があるのだ と思える日が来るのだ。」
そんなことを学びました。
ニシトアキコ学校に関しては、プライベート日記にて
また別の機会に お話したいと思います。
きっかけはいろいろでも 今にちゃんとつながっていく
「だから、私は 発信する」 というきっかけは たしかに
「尊敬する素敵な仲間の保育士たちが辞めてしまったこと」
が大きかったです。
でも
今は「そういう人を引き止めるため 生まないため」
というよりも、
「一人ひとりが自分の事をよく知って、
強みを知って、そこを生かして輝いていけるように
お互いの強みを知って、認めあい 支え合って
毎日、今を幸せ と思いながら過ごしていけたらいいな。
自分が幸せそのものだということに気が付いて
過ごしていけるといいな。」
と 思うようになりました。
やっぱり、私は 発信します。
自分理解のススメ
保育士にこだわらず、自分にあっている
自分が本当にやりたいことをできる
楽しいと思えることができることを
私は探していきたいな と思います。
見つけていきたいです。これからも。
それは一つでなくてもいい。
たくさんあってもいい。
それが掛け算されていてもいい。
ひとつにしぼってもいい。
他のものに変わってもいい。
少しづつ変化していっても
ガラリと変わってもいい。
私は やりたいことがいろいろとありつつ、
実は、「これだー!」と心から思えることに
まだ巡り合っていないのかもしれません。
しっくりくること、それは一つではないかもしれないし、
その一つを探しているのかもしれないし、
自分でもまだわかりません。
まだまだ旅の途中です。
短所は長所 長所は強み 強みを生かした楽しい生き方を
何かを極めたい思い
私は自分の経験で語れるほど、
保育の仕事ひとつでさえ 極めてはいません。
保育は奥が深すぎて
「極めた」なんておこがましいことは
一生言えない気がします。
幼児教育、乳幼児の保育や未就学児の療育、発達支援と
仕事の専門性が移り変わってきた その強みはあります。
好きなこと〜音楽〜 を思い出す
もうひとつ、音楽が好きなのです。
特性として、相対音感だか絶対音感があるようなのです。
私を療育現場で厳しくもあたたかく育ててくださった先輩から
その能力を認めてもらい 伸ばしていただきました。
自分に自信がなくて この仕事を続けていくか
辞めるべきか悩んでいるときに
自分の能力が重宝され
自分がいてもいい
必要だ と思ってもらえる居場所を
作っていただけたことを 今でも感謝しています。
そのことも、後々 触れていきたいと思っています。
楽譜通りには弾けないけれど、
練習や努力がなくても、
聞こえてくる音楽を
それなりに表現することはできます。
保育園でうたうような曲であれば、
子どもたちが歌いやすい高さに移調して弾くこともできます。
「すごいね、どうやってやるの?教えて」
と言われても困ります。
やりかたなんてわからないのです。
聞こえてくる音が、ピアノの上に乗っている5本指をイメージして、
勝手に指が動くのです。
私にもっと、再現性の高さと器用さがあれば
よくユーチューブ動画にあがっている
たぶん同じように耳コピできる 有名なピアニストさんたちのようにも
なれていたのかもしれないですね。
せっかく授けられた能力を 眠らせず、
そこを生かしていきたいと
最近は思うようになっています。
アウトプットは大事らしい
一周まわって
そんなわけで
私は やっぱり発信することにしました。
多くの人に読まれなくても、
必要な人に 「へ〜」と思える情報が
少しでも届けばいい。
今はそう思っています。
この思いも変化するかもしれません。
とりあえず、自分のアウトプットの場を設けよう。
学んでばかりで「インプットデブ」(あんちゃさんが言っていた言葉)
にならないように。
そして、アウトプットすることで、
自分の思考の整理ができて、
自分が本当にやりたいことも見つけられるかもしれない
という期待もあります。
だから、私は 発信します!
今思ったのですが、
悩める人のため とか言ってブログをはじめたものの、
実は 自分のために書いていたりするのかもしれません。
単なる日記のようになったとしても
これを読んだ人が、
「アラフィフの人でも
この年から何やら頑張って
夢や目標を達成していることに(頭の中では既に達成している脳天気 ^ ^)
自分にも もしかしたら できるかもしれないぞ」って
いつかやろうと思っていたことを思い出して
ちょっと背中を押すような
そんな力になることができたらいいな
と 考えています。
欲張りかな。
というわけで、
やっぱり、私は いつかの自分と同じような人のために
そして、自分のために 発信します。
「だから、私は 発信します!」
次回は、〜「子育てがしんどい」人のためのアイデア(方法や考え方)〜 を紹介します。「なるほど〜」と一つでも思えることがあり、少しでもしんどさが軽減されますように。キッズアンガーマネジメントの資格を持ち、ペアトレ(ペアレントトレーニング)を学び、講座で講師をした経験も活かしながら、しんどさレベルに応じて、お話していきたいと思います。